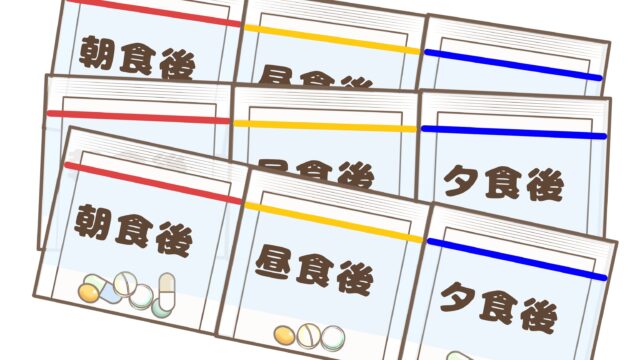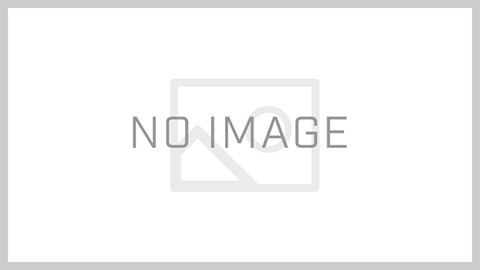今日は久々に医療・身体のこと
**Refeeding症候群(リフィーディング症候群)**とは、長期間栄養が不足していた人に急に栄養を補給した際に、体内で代謝が急激に変化し、重篤な電解質異常を引き起こす病態です。特に、リン・カリウム・マグネシウムの血中濃度が急低下し、不整脈・心不全・痙攣・呼吸不全・最悪の場合は死に至ることもあります。
いざ「やっと食べられるようになった」と安心しても、体が追いつかない場合があるのです。
なぜ起こるの?
長期間の絶食や飢餓状態では、体は糖ではなく脂肪や筋肉をエネルギー源として使う「省エネモード(ケトーシス)」になります。この状態では、インスリンの分泌が抑えられ、電解質の動きもゆっくり安定しています。
そこに急に糖質(=エネルギー)が入ってくると、インスリンが一気に分泌され、糖と一緒にリン・カリウム・マグネシウムが細胞内へ引き込まれます。その結果、血液中の電解質濃度が急激に下がり、全身の臓器が正常に働けなくなるのです。
ハイリスク患者の判定基準(NICEガイドラインより)
イギリスのNICEガイドライン(CG32)では、以下のようにRefeeding症候群のリスクが高い患者を明確に定義しています。
■ いずれか1つに当てはまると「高リスク」
- BMI < 16 kg/m²
- 過去3〜6か月で体重が15%以上減少
- 10日以上、ほとんど食べていない(絶食状態)
- 栄養補給前に血中リン・カリウム・マグネシウムが低値
■ または、以下のうち2つ以上に該当すると「高リスク」
- BMI < 18.5 kg/m²
- 過去3〜6か月で体重が10%以上減少
- 5日以上ほとんど食べていない状態
- アルコール乱用歴、またはインスリン・抗がん剤・利尿剤・制酸剤の使用歴
さらに、BMI < 14 または 15日以上の絶食状態にある場合は、「極めて高リスク」として特に慎重な対応が求められます。
具体的な対策:どのくらいのカロリーから始めるべき?
栄養補給の開始においては、次のような方針が推奨されています:
● エネルギーの開始量
- 通常は 15〜20kcal/kg/日 程度で開始
(例:体重40kgの人なら600〜800kcal/日)
極めて高リスクな場合は 10kcal/kg/日以下 から開始することもあります。
急激なカロリー増加は避け、3〜5日かけてゆっくり増やしていくのが基本です。
電解質とビタミンの補正
栄養開始前から以下のサポートが必須です:
- リン(P)・カリウム(K)・マグネシウム(Mg):補正と毎日の血中濃度モニタリング
- ビタミンB1(チアミン):100〜300mg/日を少なくとも最初の3〜5日間補給
(重症例では静注)
これらが不足したまま栄養補給を始めると、症候群が急速に進行するリスクがあります。
モニタリング項目と観察ポイント
以下の項目を毎日または数日おきにチェックしながら進める必要があります:
- 血清電解質(P, K, Mg, Na)
- 血糖値
- 体重・尿量
- 心電図(QT延長・不整脈)
- 呼吸状態・意識レベル
- 浮腫や心不全徴候(体液貯留に注意)
また、低リン血症では呼吸筋の脱力や意識障害が起こりやすく、初期症状を見逃さないことが重要です。
なぜ一般の人にも知ってほしい?
Refeeding症候群は病院だけの問題ではありません。
- 在宅介護で長期間食べられていなかった高齢者
- 摂食障害や過度なダイエットからの回復期
- 断食・ファスティング後に食事を再開する一般の人
このような場面でも起こりうるため、「ゆっくり食べさせる」「急にたくさん食べさせない」という意識は広く共有されるべきです。
まとめ
Refeeding症候群は、「良かれと思って与えた栄養」が、思わぬ危機を招くことがある――そんな落とし穴です。
リスクがある人には、慎重に・ゆっくりと・丁寧に栄養を再開する必要があります。医療職にとってはガイドラインに基づいた管理を、一般の人にとっては「焦らずに回復を見守る姿勢」を持つことが重要です。
食べることは生きること。でも、体にとってそれは「負荷」になる場合もあることを忘れないでください。
医療や薬のことでまとめたことを
発信していきます!